

| トップページに戻る | 配信日分類の総目次に戻る |
| カテゴリー分類の総目次に戻る | タイトル50音分類の総目次へ |
| カテゴリー | 文芸作品に描かれたダメダメ家庭 |
| 配信日 | 09年9月18日 |
| 取り上げた作品 | 狭き門(1909年刊行) |
| 作者 | アンドレ・ジッド(1869年〜1951年)1947年度のノーベル文学賞受賞 |
| 本とか映画とかを見たりすると、以前にも出会った設定に再度出会ったりすることもあります。 生き別れの兄弟と再会とか、記憶喪失とかの設定のケースもあるかもしれませんが、そこまでベタなりドラマティックなものではなく、ちょっとマイナーな設定に頻繁に出会ったりするもの。 単にフィクションの世界の中だけでなく、実在の人物を調べていると、フィクションの世界でよく出てきた設定と同じだったり・・・ そんな感じで、「あれっ?この設定は前にもあったなぁ・・・」と思ってしまった設定として、「ジャンセニスト」あるいは、「ジャンセニスト的キャラクター」という設定があります。ジャンセニストについては、例のウィキペディアを使ったりして調べてみてくださいな。 私が、本を読んだり、映画を見たりすると、割と遭遇したりする設定なんですよ。 じゃあ、そのジャンセニストって、簡単に言うと何? フランスなどを中心に活動したキリスト教の一派で、日々の生活においては倫理的に生きることを求め、教義的には現世のはかなさを強調する宗派です。現世でどんな努力をしても、来世での幸福とは無関係・・・極端に言うと、そんな発想を持っている宗派なんですね。宗教改革のカルヴァンとは人的には直接には関係ないようですが、発想の流れは受け継いでいるといえます。別の言い方をすると、ユグノーの後継者であり、フランスのピューリタンと言えるでしょうか? あるいは、融通を利かせるというよりも、原理原則を重視する宗派とも言えるでしょう。 私がこのジャンセニストという用語と出会った最初が、今回取り上げる「狭き門」という小説の中です。ちなみにこの「狭き門」は、フランスの作家アンドレ・ジッドの作品です。ジッドは1947年度のノーベル文学賞受賞者であり、今回の「狭き門」は、有名な作品ですから、実際にお読みになった方もいらっしゃるのでは? ちょっと調べてみたら、初版が1909年とのことで、今年でちょうど100周年ということになります。私の文章が100周年記念になるのかな? このタイトルの「狭き門」とは、新訳聖書にある「狭き門より入れ!」・・・つまり自堕落に生きないで、自分を厳しく律しなさいな・・・そんな発想を連想させるもの。 この「狭き門」のあらすじとしては、以下のようなものになります。 父親が早くになくなったジェロームは、裕福な家庭の青年。彼は母親によって育てられている。ジェロームは母の弟の長女で2歳年上のアリサと恋愛関係になる。アリサもジェロームも、優秀な頭脳を持ち、熱心なクリスチャン。2人は婚約寸前というレヴェルまで関係が進むが、アリサは、ジェロームと距離を取り始め、顔を合わせなくなってしまう。やがてアリサは衰弱し、パリの養護院で死んでしまう・・・ ・・・あらすじだけだと、訳が分からないでしょうが、愛し合っているはずなのに、一緒にならない2人・・・というストーリーです。 ちなみに、アリサの母親は、アリサが思春期の頃に、若い男と駆け落ちしていなくなってしまいました。その母親は、フランスの植民地であるアフリカのアルジェで養子となった子供。いわば南方由来の人といえるわけ。 最初に書いたジャンセニストの話に戻りますが、私が別の機会にそのジャンセニストという言葉と出会ったのは、フランスのアラン・コルノー監督の「めぐり合う朝」という映画においてです。その映画は今はレンタルショップにはないかもしれませんが、その原作本をおいてある図書館はあるでしょう。そこで舞台となる家庭がジャンセニストだったんですね。 あるいは、ジャンセニストの有名人となると、パスカルがいます。気象予報で登場してくる「○○ヘクトパスカル・・・」とかの物理単位にまでなっている有名な方。あるいは「人間は考える葦である。」という言葉は皆さんもご存じでしょう。 それ以外に有名人となると、劇作家のラシーヌがいます。 このメールマガジンは、キリスト教の一宗派の問題を考えることを目的とはしておりません。あくまで家庭問題を考えるために、様々な事項を参照しているだけです。 さて、これらのジェンセニストには、特徴的なキャラクターがあります。 母親というか、母性の影がないんですね。 パスカルは父子家庭の出身です。厳格な父親のもとで育った人。 あるいは、劇作家のラシーヌは両親が早くに亡くなり、修道院付属の宗教学校を出た人。当然のこととして、実感としての母親なり母性とは縁遠い。ラシーヌの代表作として「フェードル」という作品がありますが、その「フェードル」においては、王妃フェードルが自分の義理の息子である王子イポリートに恋慕してしまう・・・というストーリーを持っています。母親と言っても血が繋がってるわけではないんだから、義理の息子に恋慕するのは勝手でしょう。しかし、そんな恋慕は女性的かもしれませんが、母性とはかけ離れているでしょ? ちなみに映画「めぐり合う朝」においても、舞台となっている家庭は、父子家庭です。こちらも厳格な父親の家庭。 これらの登場人物は、結局は衰弱して死んでしまうことが多い。もっと端的に言うと鬱病傾向がある。「めぐり合う朝」での主役格の女性は、鬱病で自殺。あるいは、パスカルだって晩年は鬱病っぽい。 ジャンセニスト・・・母性の不在・・・鬱病・・・ どうも、これらは繋がっているようだ・・・ 私としては、そんな思いを、ずっと持っていました。 直接的にはジャンセニストではないのですが、バルザックの「谷間の百合」のアンリエットも、母親への反発、そして現実逃避傾向、そして鬱病による衰弱死と、これらの設定に近いスタンスです。 ダメダメ家庭の周辺では、この手のキャラクターが実に多いわけ。 前回配信の文章で、ダメダメ家庭の人間は「正義感が強い」ということについて書いております。正義感が強いということは一見いいことのように見えるわけですが、その裏面を考えてみると、「汚れとの付き合い方がわからない」人間と言えるわけです。 母性とは、その心理的な意味としては、「汚れを受け入れ、そして浄化する存在」となります。母性というものは、芸術の分野においては、大地や海とのつながりで表現されたりしますが、「汚れを受け入れ、浄化する存在」という意味では、母性も、大地も、海も、実に繋がっているでしょ? 汚れを受け入れ浄化してくれる存在としての母性がない場合には、汚れは消えることがない。だからこそ「絶対に汚れてはならない!」と切羽詰まった心情を持つことになる。 「絶対に汚れてはならない!」という心情があるがゆえに、過度なモラリストとなったり、様々な面で教条的で原理主義的な傾向を持ってしまう。自分で解釈し判断するのが怖いわけ。自分の判断から、世俗の「汚れ」とのつながりを感じてしまう。 「絶対に汚れてはならない!」そんな感じで切羽詰まっていたら、気晴らしもできませんし、精神を使い果たして、鬱病になってしまうのも当然のこと。 さて、今回取り上げるジッドの「狭き門」ですが、主人公のジェロームは、父子家庭ではなく、死別による母子家庭の出身です。あるいは相手方のアリサも自分の思春期に母親が駆け落ちでいなくなったわけだから、母親の記憶は濃密に持っている。そういう意味では、母親はいるわけ。 しかし、母親がいても、そこに母性があるかというと、また別問題となる。 ジェロームの母親は、厳格な母親であり、「汚れを受け入れ、浄化する」存在とは言えない。 あるいは、アリサの駆け落ちした母親は、自分の情欲の赴くまま突き進んだわけだから、汚れを浄化するどころではない。アリサとしてはそんな母親に対して反感を持っている。だから「あんな風になりたくない!」と思っている。 つまり、ジェロームとアリサの2人とも、母親がいても、母性がわからないわけ。あるいは、生物的に母親がいても、心理的には母親がいない・・・そうとも言えるでしょう。 さて、7月において人間の心理的ベースについての文章を集中的に配信しております。 新生児の頃に、養育者からの的確な反応を受けていない人間は、他者を心理的に認識することができない状態。別の言い方をすると、人間とマネキンとの差が、心理的に認識できないわけです。 その当人自身としてもボンヤリとした「うつろな」キャラクターだし、周囲を認識するにあたっても、ボンヤリとしてしまう。 このような事例は、アルベール・カミュの「異邦人」でのムルソーがまさにその典型と言えます。 自分自身なり自分の周囲を、心理的にはボンヤリと認識している・・・くだけた言い回しだとそんな言い回しになるわけですが、そんな状況を、より宗教的な言い回しで言うと、「現世のはかなさ」となるでしょ? 反応を喪失した抑圧的なダメダメ家庭出身の人間としては、ジャンセニズムとは実感的にフィットしやすいわけ。実体感の欠如・・・つまり「現世のはかなさ」という発想によって結びついてしまうことになる。 抑圧的なダメダメ家庭においては、他者という存在を、心理的に認識できないわけですが、抑圧的なダメダメ家庭と言っても、様々なパターンがある。 知識豊富で知的に鋭敏なパターンもあったりする。 そうなると、他者という存在は心理的には認識できなくても、知識力によって、他者を認識する・・・そんな芸当をするようになってしまう。 その初歩的なレヴェルだと、カテゴリー分類ばかりの人間になったりする。 カテゴリーで分類して、そのカテゴリーの話ばかりして、相手そのものを見ようとしなくなってしまう。しかし、相手そのものは、心理的には認識できないんだから、カテゴリーで語るしかないわけ。 知力が発達していないと、その手のカテゴリー分類に安住するレヴェルで止まってしまうわけですが、知力が発達していると、相手に様々な言葉や概念の衣を着せて、その衣によって、相手を認識する方法を取ることができる。 単純なカテゴリー分類を超えて、それこそ宗教的な蘊蓄とか、文芸的な修辞とか、歴史的な故事来歴とか、学者の学説とか・・・色々と説明の言葉で、相手を何重にも覆ってしまうわけ。相手を言葉で覆ってしまえば、心理的に認識できていない存在でも、「覆い」によって、認識することが可能になるでしょ?裸だと見つけられない透明人間だって、服を着れば見つけられますよ。だから、どんどんと概念の服を着せてしまう。 その手の「覆い」としての言葉も、他者という存在を心理的に認識した上でのことだったらいいわけですが、そもそも他者という存在を心理的に認識できないがゆえの、そんな言葉なので、主従が転倒してしまっている。抑圧的な人間は、説明としての言葉が主であって、説明対象の人間そのものは従の存在なんですね。 しかし・・・そんな言葉や概念の服を何重にも着せられた側はたまったものではない。まさに身動きが取れず、窒息してしまう。 そんな基本?がわかっていると、この「狭き門」という作品の基本的な流れも理解しやすいでしょう。 ジェロームは、アリサを覆う言葉や概念を見ているだけで、実体としてのアリサ本人は見ていない。というか、心理的には「見たくない」と思っている。現実のアリサと直接に向き合って、現実的な問題が認識されたら、それに対処しなくてはならない。しかし、それは「正義感の強い」「倫理的な」、別の言い方をすると「汚れを恐怖する」人にはできないこと。だからジェロームはアリサとの間に距離を取りたいと、本音では思っている。 ジェロームはアリサに対して「キミに会いたい!」などと言ったり、手紙で書き送ったりしますが、本音では違っているわけ。言語と実体のプライオリティが逆転している人間にしてみれば、「会いたい!」という言葉が重要なのであって、だからこそ、実際に会ってしまうと「会いたい」とは言えなくなってしまう。それは不都合なこと。 会いたいと言い続けるためには、実際に会うわけにはいかない。 そして、そんな屈折した人間であるジェロームの相手としては、アリサは実にうってつけ。 そもそもアリサは「人に合わせすぎる」キャラクターなので、そんな屈折した要望にも合わせてくれる。それにジェロームの屈折した要望を、無意識的に認識できるだけの鋭敏さも持っている。鈍感な人間だったら、言葉と心理が一致していないジェロームの心情なんて理解不能ですよ。 あるいは、自分の母親が駆け落ちしたので、その反動から、アリサはその母のようには自分に正直になれない。だから、どうしても人に合わせてしまう。 結局はアリサは鬱病で死んでしまうわけですが、ジェロームにしてみれば、もともと「覆い」の方が重要だったわけで、実体としてのアリサ本人が死のうが生きていようが、あまり関係ない。だからこそ、まさにアリサの思い出を抱いて生きていることになってしまう。 アリサが生きている頃から、アリサの思い出が主であり、実体は従の形で認識していたわけです。 アリサはジェロームの本音に合わせている。婚約をしないことも、距離を取ることも、自分が死ぬことも、実は、ジェロームの本音の希望。アリサはその希望に合わせたわけ。 「愛している!」という言葉が主であって、愛の感情は従の存在。 真実なのは「キミに会いたい!」という言葉の方であって、だからこそ、実際には会いたくない。 言葉と心理が一致していないので、この「狭き門」においては、後半においては手紙とか日記が多く登場してきます。登場人物の個人的な独白なり、相手に宛てた言葉はあっても、それが作者による客観的な描写かというと別。そのような言葉と心理の分離、あるいは、主観と客観の乖離は、それこそバルザックの「谷間の百合」が書簡体の小説となっている理由と同じなんですね。 この「狭き門」では、ジャンセニスト的キャラクターという設定は、単に登場人物の設定というレヴェルを超えて、作品の中心テーマに近い扱いとなっている。だからジャンセニストであるパスカルなりラシーヌも読者に強調された形で言及されます。ジャンセニストが持っている「母性の欠落」「汚れへの恐怖感」こそが作品のテーマとなっているわけです。 ジェロームとしては、自分の母親を認識する際にも、実体感がなく、言語や概念の集約として認識している。実体感がないので、基本的には女性という存在が何もわからない。「女性というものがわかっていない」という言葉は、バルザックの「谷間の百合」でフェリックスが言われていました。女性を教科書的には語れるけど、実体として実感が伴った形では語れない。それだけ、自分が一番よく知っている女性・・・つまり自分の母親を、実感として認識していないわけです。そのようなことは、何もフェリックスやジェロームのような男性だけでなく、女性にも同じことが起こるもの。一番よく知っている男性・・・つまり自分の父親を実感として認識していないと、やたら概念的でカテゴリー分類だけになってしまうでしょ? ちなみに、アリサは3人兄弟の長女です。3歳下にジュリエットという情緒豊かで元気な妹がいて、その下にロベールという、いささかできの悪い弟がいる。ジュリエットとロベールは、駆け落ちする前の母親とも良好な関係でしたし、まだ小さかったので、母親の駆け落ちによって、大きな心の傷を受けてはいない。ジュリエットもロベールも、ポジティヴな方向での母性の残像を持っている。 ジュリエットは、思春期の頃は、姉の恋人であるジェロームを好きになってしまったりと、感情面は豊か。やがては、農業経営者と結婚し、かっぷくのいい、世話好きの母親となる。ジュリエットは母性も持っているわけですし、農業経営という設定が指し示すように、大地というものを持っている。「自然な感情というものに対し、自然な形で付き合える」人間なんですね。 この「狭き門」の最後は、アリサの死後10年以上経って、ジュリエットの元をジェロームが訪れるシーンです。姉であるアリサの思い出の品々を見ながら涙するジュリエット。 実は、この「狭き門」という作品には、涙のシーンがほとんど出てこない。 愛し合いながら、一緒にならないんだし、主要人物が死んでしまうんだから、もっと泣けばいいのに・・・ しかし、そんな自然な感情を持っていない・・・それがジェロームであり、アリサというわけです。 ジェロームもアリサも愛の言葉は、実に見事なもの。しかし、夕陽を浴びながら、かっぷくのいい女性が、亡き姉を思い出し、声を押し殺して涙する姿の方が本質的な、別の言い方をすると、実感を伴った愛の姿じゃないの? 自然な感情というものは、現世的な汚れに繋がるわけだから、「汚れを受け入れ、浄化する」ものを持っていない人間には、抵抗があったりする。 じゃあ、自らを「受け入れてくれるもの」・・・それはどこにあるのか?いったい何なのか? もっと極限の状態だと、死に場所はどうなるの?生の終わりに何を求めるの?自分の何を受け入れてほしいの? あらすじにも書きましたが、アリサは、最後に、パリに一人で死に出かけ、養護院でお亡くなりになりました。アリサとしては、もっと別の選択もあったはずです。 どうせ死ぬんだから、それこそ、恋人だったジェロームのところに出掛け、そこで死んでもいいし、嫁いでいる妹のところに出かけて、そこで死んでもいいのでは?あるいは、住んでいる場所でそのまま最後を迎えてもいいのでは?愛しているものに囲まれて死にたい・・・そんな感情が罪なの? どうしてわざわざ見知らぬ土地で、見知らぬ人に囲まれて死のうとするの? 逆に言うと、「生を背負った汚れた自分」を受け入れ、浄化してくれる「具体的な」存在を、確信していないわけ。最後になって付き添うのが家族でも、恋人でも、そして故郷でもない・・・アリサは還る場所を持っていない人なんですね。 前回配信の文章にも書きましたがヘルマン・ヘッセの「知と愛」の中で「君には母がない。だから死ぬことができない。」という言葉がありましたが、「狭き門」でのアリサも、まさに死ぬことができない人間。だからこそ、鬱病になり、結果的に死んでしまうことになる。 自分の罪なり汚れを自覚しているがゆえに、浄化のための母性を求める発想は、それこそ、キリストよりも、その母であるマリアの方をありがたかるマリア崇拝の発想に繋がってくる。もちろん、ゲーテの「ファウスト」の終幕が、まさにその構図となっているのは、ご存じの方も多いでしょう。 さて、色々と本を読んでいると、「この設定にまた出会ったよ!」と思ったりすることが多いと、最初に、書きましたが、ちょっと変形で、「またこの人の紹介文が書いてあるよ!」なんてことも多いもの。 実は、私が本を読んだりすると、その巻末にある「解説」において、ドイツの文豪であるトーマス・マンによる紹介文に遭遇することが多いんですね。 それこそ、トルストイの「アンナ・カレーニナ」を、マンが「完璧な小説だ。」と評したのは有名ですし、チェーホフに対して、「反語的な表現が多い。」とかのマンによる指摘があったりします。 ほとんど解説文を読まない私ですが、巻末をチラっと見ていると、トーマス・マンの名前があって、「あれっ?またトーマスじゃないか!よく会うねぇ・・・」と思ってしまうわけ。 文学研究者による解説には閉口し、失笑する私ですが、トーマス・マンによる紹介文にはうならされ、苦笑することも多い。 作者のジッドについては、そのトーマスさんは、こんな紹介文を書いています。 最後に、その紹介文を載せておきましょう。 「短見な道学者は彼に非難を投げ掛けたけれども、彼は精神の好奇心の極点を持ち続けていった。彼の場合におけるような高度の好奇心は、懐疑主義となり、この懐疑主義はさらに創造力と変わってくる。彼はこの好奇心を、彼の好きなゲーテとともに分け持っていた。彼はゲーテのように、絶え間ない衝動によって動かされ、探求の方に絶えず押しやられていた。魂の平穏無事や逃避は、彼の取らないところだった。不安、創造的な懐疑、無限の真理探究が、彼の領分だった。そしてこの真理の方へ、英知と芸術とによって与えられたあらゆる方法を以て、進もうと努力したのだった。」 (終了) *************************************************** 発信後記 本文ラストのトーマス・マンによるジッドについての見解の文章をお読みになった方は、「この指摘って、あの人にもそのまま使えるじゃないの?」と思った方もいらっしゃるかも? ちょうど100年前に活躍した作曲家にして指揮者のグスタフ・マーラーの特徴と、完璧に「かぶる」んですね。まあ、他にもかぶる人はいるでしょうが、マンが、ジッドについての指摘の文章をまとめた際には、マーラーのことも頭にあったことは確実でしょう。 たぶん、マンが上記の文章をまとめていた際には、マーラーの交響曲第8番・・・たぶん、第1楽章の方・・・がアタマの中で鳴り響いていたのでは?ちなみに、マーラーの第8番は、来年が初演100周年だから、来年は結構頻繁に演奏されるだろうなぁ・・・ ちなみに、その曲の1910年の初演のリスナーの中には、トーマス・マンもいました。 マーラーの交響曲第8番は、完成したのは1907年。ジッドの「狭き門」と、ほぼ同じ。 外見は、かなり違っていても、その精神は共通しているわけ。 マーラーの交響曲8番について、第1楽章については、神をたたえる讃歌のような解説をされたりしますが、何も神を賛美しているのではなく、「徹底的に真理を求め続ける」心情を表現しているわけですので、マンによる上記の文章に当てはまるわけ。そして、ゲーテとともに言葉を分け持つ、第2楽章に続くことになる。 創作者が他の創作者に言及したりするのは、何も批評のためではなく、別の創作者の作品との共感なり、不快感から、逆に言うと、自分自身が見えてくるわけ。 他の創作者に言及した文章は、まさに自分自身の内面にあるイデアを、洞窟の壁に映したようなもの。結局、映っているのは、自分自身。 別の言い方をすると、移ろい行くものは、永遠なるものの比喩に他ならない・・・というわけです。 |
|
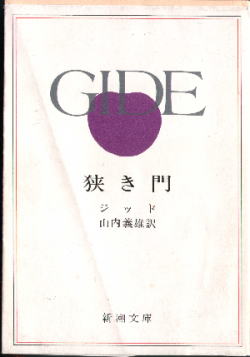 |
|
| R.10/12/27 | |